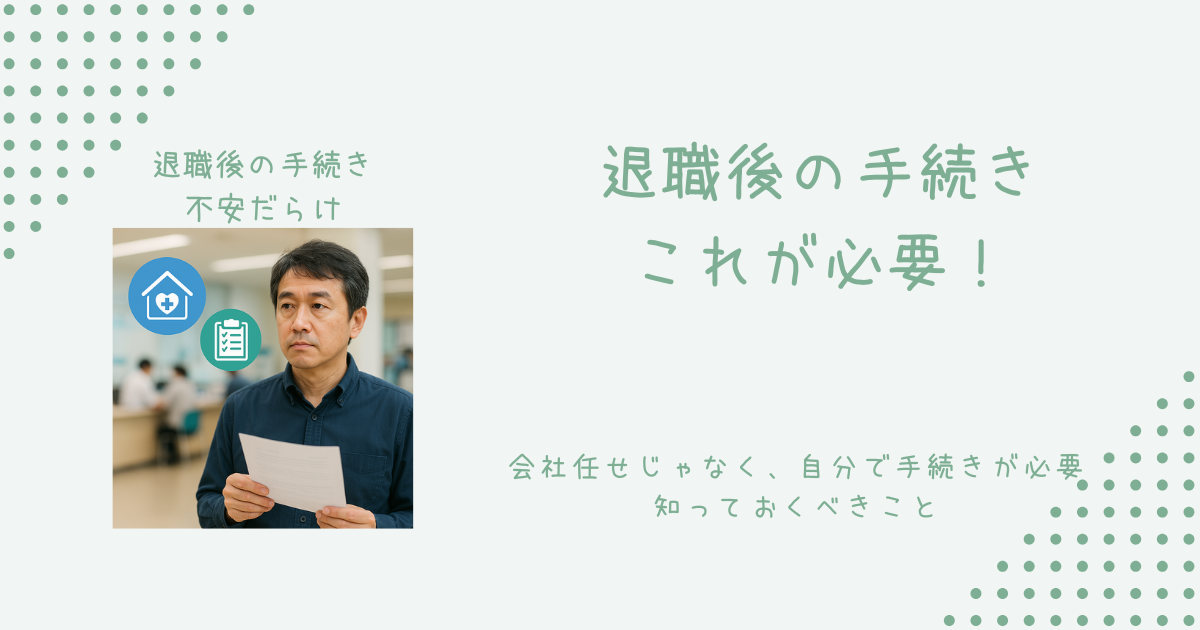前提:自分は58歳で早期退職、その後2つ目の会社で契約社員として3年間働いたサラリーマンとしての体験談です。個人が情報をまとめたものです。情報の正確性を保証するものではありません。
退職後の手続きまとめ|税金と保険のポイント
2025年7月末 2つ目の会社を、61歳で退職しました。
ここでは、自分が実際に行った退職後の手続きを整理しておきます。
退職後に必要な手続きは、大きく分けて 「税金」 と 「保険」 の2つです。
これまで給与から自動的に天引きされていたものを、自分で納付・申請する必要があります。
1. 社会保険の手続き
今まで、給与天引きされていた、社会保険の項目は以下の4つです。
- 雇用保険
- 健康保険
- 年金保険
- 介護保険
これらは、退職後どのようになるのか整理してみます。
1-1. 雇用保険
退職すると雇用保険料の支払いは不要になりますが、失業保険を受け取るための手続きが必要です。
会社から送られてくる 「雇用保険被保険者証」 と 「雇用保険被保険者離職票(1・2)」 を持ってハローワークへ行きましょう。
雇用保険は、在職中に支払ってきた保険料で、失業時の生活を支える仕組みです。
退職したら、忘れずにハローワークへ行って失業給付の手続きをしましょう。
早めに次の就職先を見つけて就職するのが一番いいと思っていますが、失業保険の手続きをしないと、給付されないので、まずは、行ってきます。
病気になったら、病院に行って健康保険証を見せることで、保険が適用され自己負担3割負担で済むように、雇用保険は、失業したらハローワークへ行って、雇用保険被保険者証を提出することで、失業保険の請求ができます。
ハローワークでの申請から給付まで実体験を、次回、まとめてみます。
1-2. 年金保険
国民年金は20歳以上60歳まで加入が義務付けられています。会社員は給与天引きで徴収されています。
私の場合は60歳を過ぎていたため、国民年金の納付は不要でした。
- 国民年金:60歳で払い込みが終了。
- 厚生年金:働いている人のみ加入。
退職後は 第2号被保険者 → 第1号被保険者 へ区分が変わります。
扶養中の妻は 第3号被保険者 → 第1号被保険者 となり、60歳まで国民年金の納付が必要です。手続きは市町村役場で行います。
1-3. 介護保険
介護保険料は40歳から徴収されます。
- 40~65歳未満:第2号被保険者(会社員の間は、天引き徴収)
- 65歳以上:第1号被保険者(年金から天引き)
退職後は健康保険料と一緒に介護保険料を支払います。雇用中は会社と折半でしたが、退職後は全額自己負担になります。
1-4. 健康保険
退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入
- 任意継続で会社の健康保険を継続
- 家族の扶養に入る(年収制限あり)
私は 任意継続 を選びました。保険証は返却し、マイナ保険証を利用します。
手続きは 任意継続被保険者資格取得申請書 などを20日以内に提出。
申請後、「資格情報のお知らせ」が届き、マイナンバーと健康保険の紐付けが完了します。
次回、病院でマイナ保険証を試してみます。
<退職後の健康保険について3つの選択比較>
| 項目 | 国民健康保険 | 任意継続被保険者 | 配偶者の扶養 |
|---|---|---|---|
| 加入手続き先 | 市区町村役所 | 前の健康保険組合 | 配偶者の勤務先 |
| 加入条件 | 退職して健康保険がない人 | 資格喪失日から20日以内に申請 | 年収130万円未満など |
| 保険料計算 | 所得に応じて計算 | 在職中の標準報酬を基準 | 保険料負担なし |
| 保険料負担 | 全額自己負担 | 全額自己負担(会社負担分も) | なし |
| 有効期間 | 制限なし | 最長2年間 | 扶養条件を満たす限り |
| メリット | 所得が低いと安い場合あり | 国保より安くなる場合も | 無料で医療保障あり |
| デメリット | 所得が高いと高額になる | 所得に関係 | 条件を超えると脱退 |
詳細は、それぞれの担当へ確認して、情報を集めましょう。
2. 税金の手続き
2-1. 住民税
住民税は前年1月~12月の所得で計算され、6月から翌年5月まで徴収されます。
退職後に収入がなくても、翌年5月までは納付が必要です。退職後は役所から 納税通知書 が届きます。
2-2. 所得税
サラリーマン時代は、毎月の給与計算で源泉徴収されていました。
退職した場合は、翌年2月の 確定申告 で精算します。
多くの場合、税金が還付されますが、給与以外の所得がある場合は追加納税になることもあります。
まとめ
- 退職後は「税金」と「保険」の手続きを自分で行う必要がある。
- 雇用保険はハローワークで申請し、健康保険は国保・任意継続・扶養のいずれかを選択。
- 年金や介護保険の区分も変わるため、市町村役場での手続きが必要。
- 住民税は後払い方式で、翌年5月までは支払いが続く。
- 所得税は翌年の確定申告で精算する。
会社員時代は、会社が一括でやってくれていた手続き。退職して自分でやってみると、そのありがたさがよく分かります。