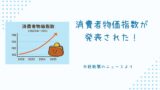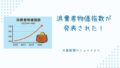2025年8月23日 日経新聞では、日本と中国の物価について対照的な記事が出ていました。
中国で出前アプリを使うと無料?
中国、出前アプリで無料・高級品値引き...日本の震災後並みデフレ圧力
中国で景気停滞に伴う過剰な値引きが目立ってきた。市民が日常的に使う出前アプリでは無料で商品を提供するサービスが登場し、高級酒やブランド品も値崩れがみられる。
日本経済新聞 2025年8月23日の記事より引用 有料会員以外は一部のみの表示です。
アリババが一兆円と投じて原資とし出前アプリを使えば無料にするサービスを始めたことや、お酒などぜいたく品も8割引きで販売するなど、デフレ状態になっているとのニュースです。
中国政府も警告をならし、無秩序な低価格競争を規制すると言ってます。
景気が悪いので、どんどん消費がシュリンクし、それでも需要を喚起させるために大手は極端なサービスで需要の取り込みをしているようです。
日本はインフレというニュース
8カ月連続で3%インフレ、2%台の通年予想とズレ 想定超す食品高
予想を超える物価高が続いている。総務省が22日発表した7月の消費者物価指数(CPI)は生鮮食品を除く総合の指数が前年同月比3.1%上昇した。食品の値上げが止まらず、8カ月連続で3%台となった。
日経新聞 2025年8月22日の記事より引用 有料会員以外は一部のみの表示です。
物価高が続いている主因は食料品の上昇だ。7月は生鮮食品を除く食料が8.3%上昇した。
一方、日本では物価の上昇が止まりません。2025年7月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合で前年同月比3.1%の上昇となりました。特に食料品の値上げが顕著で、インフレの主因となっています。
コメの高騰のニュースは最近、小泉大臣の発言も毎日のようにテレビで取り上げられ国民の関心も広がっています。ほんとにコメの値段は急騰しました。一時期は、コメが店頭からなくなりました。
需要が多く、供給がないからコメの値段が上がっているというわけでもなさそうですが、なんで急に2倍にもあがるのでしょう?
インフレ率は2%ぐらいがちょうどいいのでしょうが、実態は3%超えでした。
企業もこの時期に、相次いで値上げを発表しています。もう、毎月テレビでも値上げのニュースが出て、慣れてきた感じはあります。またか。。。と。
参考:前回の記事
大企業は、直接お客さんに販売価格へ転嫁できますが、中小企業はしんどいです。
でも、中小企業にも、賃金上昇や、材料費の高騰、運送費の高騰を正当な理由があれば、ちゃんと価格に転嫁させて、お客さんに説明していくようにと国からも指導が入っています。買う側の大企業も今までのように冷たくあしらうと、指導が入ります。
物価上昇だけでなく、賃金も上昇し正常な上昇回転からの経済発展を望みます。
2つの国で異なる現象
中国と、日本のニュースを見て経済が同じように動いているわけではないんだと実感します。
それぞれのお国の事情があるようです。
特に中国は、ちょっと前まで急激な成長をして、バブルと言われていた時もありますが、ここへきて景気停滞というニュースが目立ちます。今回の記事では、とうとうゼロ円で出前するというところがニュースになりました。
比較してみた。
物価上昇も、景気停滞もどちらの状況も生活はしんどいです。
| 中国(デフレ) | 日本(インフレ) | |
|---|---|---|
| 現状 | GDPデフレーター▲1.3%(9期連続下落) | CPI +3.1%(8カ月連続3%台) |
| 主因 | 消費低迷、過剰生産、値引き競争 | 食料品高、人件費・物流費上昇 |
| 象徴的な現象 | 出前アプリ「ゼロ元」、高級酒・ブランド品の値崩れ | 食料品2100品目以上が値上げ、最低賃金引き上げ |
| 政府の対応 | 低価格競争の規制を表明 | 賃上げ推進 → 物価転嫁が加速 |
日本はすでに、高度経済成長もオイルショックも、バブルもバブル崩壊も、デフレも経験しています。
まとめ
中国は「需要不足で価格が下がるデフレ」、日本は「コスト増を価格に転嫁するインフレ」という、正反対の状況にあります。
共通しているのは、どちらも消費者・企業に大きな負担を与えている点です。
これから日本は、少子高齢化の中でどうやって経済を発展させるか? AIを活用して効率化していくか?などが課題になりそうです。
世界経済において中国と日本の動向は無視できないだけに、今後の政策対応や物価の推移は注視していく必要があります。