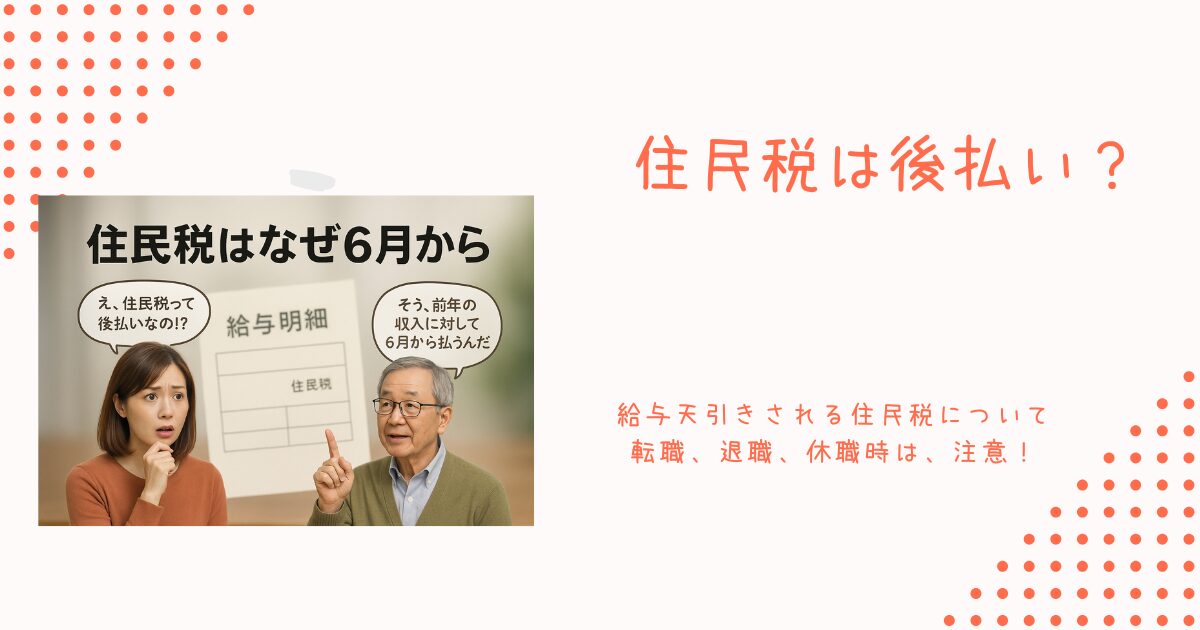※ここで紹介しているのは、GGが個人で勉強したものをまとめたものであり、情報の正しさを保証するものではありません。詳しくは、税理士さん、社労士さんなど専門家の意見も参考にしてください。
給与明細にある「住民税」は、なぜ6月から?
給与明細に記載されている大きな天引き項目は、税金と社会保険です。税金には2種類あり、「所得税」と「住民税」がありますね。
前回、所得税は「前払いの仮払い」であることを説明しましたが、今回は「住民税は後払い」についてお話しします。
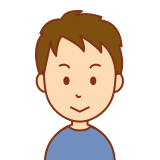
所得税は、前払いの仮払い、年末調整で確定するんだったね。
でも、住民税は、後払いなんだ。
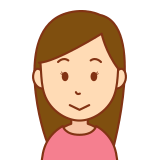
え?よくわからないわ。教えて。
住民税は「前年の収入」に基づいて課税される
住民税の計算は、前年1月〜12月の収入をもとに行われます。そして、1月1日時点で住んでいる自治体に納める仕組みです。
このため、実際に住民税の天引きが始まるのは、毎年6月からになります。
1年遅れの課税となるため、収入に変動があった場合は注意が必要です。
【体験談】海外赴任から帰国後に住民税が激増!
実際に私(GG)も体験したことがあります。
私は2022年3月末まで海外赴任しており、現地に住所を移していたため、その年の住民税は0円でした。
2022年4月から日本の本社に帰任し、市役所で転入届も提出しました。
最初の2022年4月からの給与から住民税は天引きされていませんでした。
するとどうでしょう。翌年2023年6月から、突然住民税がドカーンと天引きされてびっくり!
理由を調べたところ、こういうことでした:
- 2022年1月1日時点では日本に住所がなかったため、2022年の住民税は課税されない
- 2022年4月以降の収入が、2023年の住民税の対象になる
つまり、1年遅れて課税される仕組みを知らないと、急に手取りが減って驚くことになります。
転職・退職・休職にも要注意!
この住民税の仕組みは、転職・退職・休職のように収入が変わるタイミングでも注意が必要です。
収入がなくなっても、前年の収入に基づいて課税されるため、翌年の6月以降も住民税の支払いが続きます。退職した翌年の収入ゼロになった場合は、大きな負担となります。
住民税の計算方法
住民税の税率は一律で10%(市区町村税6%+都道府県税4%)です。
課税対象となるのは、収入から各種控除を引いた「課税所得額」です。
収入から控除額を引いて求めた課税所得額に対して税率がかけられます。
令和7年から税制控除があって控除額が変更になる。
住民税を計算するときの控除。基礎控除の改正は所得税のみで住民税は対象外です。
給与所得控除の改正は、所得税も住民税も対象です。
| 控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 給与所得控除(最低保障) | 適用(65万円) | 適用(65万円) |
| 基礎控除 | 適用(最大95万円) | 適用なし(引き上げなし) |
参考:前回の記事 「所得税の税制改正」についてです。
まとめ|住民税は“あとから来る”!
- 住民税は前年の収入に基づいて計算される
- 毎年6月から天引きが始まる
- 転職・退職・帰国などのタイミングで注意が必要
自分の給与明細やライフイベントに合わせて、住民税の仕組みを知っておくことはとても大事です。
思わぬ出費でびっくりしないよう、しっかり備えておきましょう!